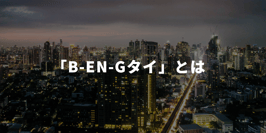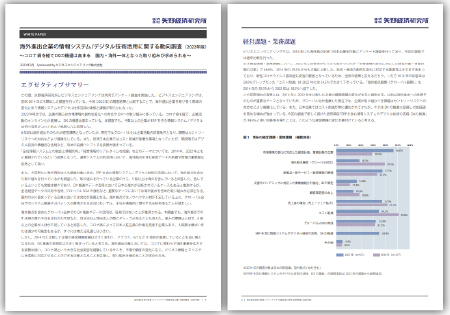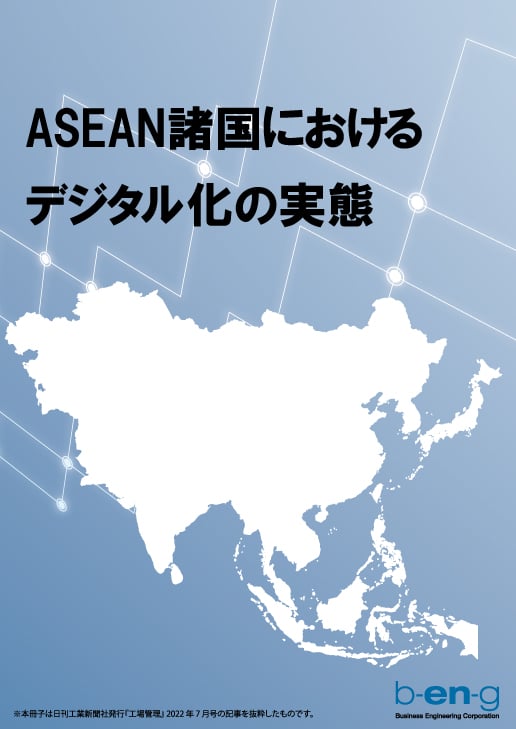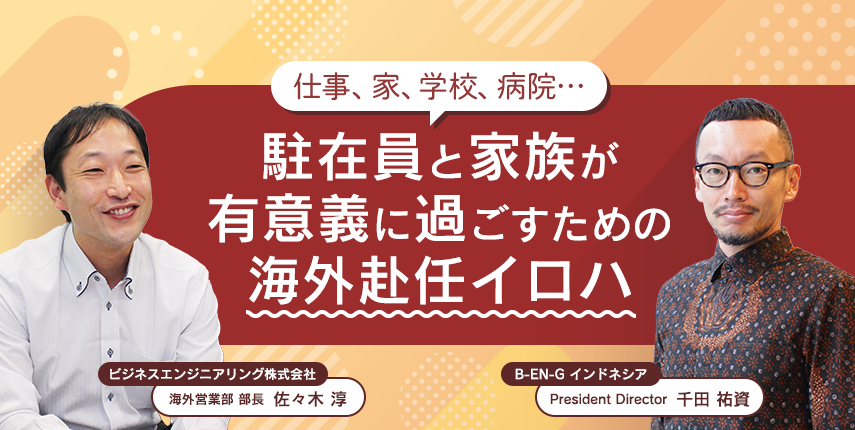関係の構築は「あだ名」を覚えることから?初めてのタイ駐在を円滑に進めるためのポイント

【話者紹介】

内田 雅也(うちだ・まさや)
Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. (B-EN-Gタイ)
Deputy Managing Director
2002年入社。日系製造業の海外拠点に対するシステム導入や運用サポートに長年携わり、2014年にインドネシアで初めての海外駐在を経験。2021年からタイに赴任。

小川 雅敏(おがわ・まさとし)
Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd. (B-EN-Gタイ)
General Manager
2003年入社。国内外で製造管理システムなどの導入支援を多数経験し、2024年7月から初の海外駐在でタイに赴任。趣味は旅行やバレーボール。
「パクチーは食べられるか」
――2024年、タイに赴任した小川さん。初の駐在までの経緯を教えてください。小川 雅敏氏(以下、小川氏): もともと海外の人と一緒に働くことに憧れがあり、入社後も海外出張で現地工場にシステムを導入するプロジェクトを多数こなしてきました。入社して15年近く経った頃から、「海外駐在をしてみたい」というキャリア志向が明確になり、前々から希望を出していました。
中国やシンガポール、アメリカなどの候補があったなかで、「タイに赴任してくれ」と内示が出たときは嬉しかったですね。新卒入社後初めて関わったプロジェクトが日系企業のタイ工場へのシステム導入で、数か月間滞在したことがあったんです。運命を感じました。
――しかし出張と駐在では大違いですよね。不安に思ったことはありましたか。
小川氏:日本で済ませないといけない手続きについて、内田さんに色々相談しました。現地に住んで働くとなれば、ビザに加えて就労許可も必要になります。ホテル生活ではなく居住するわけですから、現地の不動産屋を訪ねて家探しをする必要もありました。手続きが一通り終わるまでに、2か月半くらいかかりましたね。
――内田さんは2021年からタイで働いていますが、赴任が決まった小川さんに助言したことはありましたか。
内田雅也氏(以下、内田氏):「日用品はここで買える」とか、「辛いものが食べられるか」「パクチーは食べられるか」とか、最初はそんなコミュニケーションが主だった気がします。お互い入社年次が近かったので、気軽に話せました。
駐在が初めての人にとっては、「日本のものがどこまで手に入るか」は、大事なポイントだと思います。お菓子一つとっても、銘柄によって買えるものと買えないものがある。タイ料理が苦手なら、ふりかけやインスタント味噌汁を多く持ってくるとか、赴任前の工夫で補えることもあるので、そこは伝えた気がします。
小川氏:「食」という意味では、いざ赴任すると、タイは比較的恵まれていました。もともとタイ料理は好きでしたし、日本料理店もそこら中にあるので。結果的には、困ったことはなかったですね。
――先ほど話題になった家探しについては、どうでしょう。
内田氏:うちは家族帯同で、小川さんは単身だから、エリアも含めて少し事情が違うんですよね。意外とそこでアドバイスできることは少なかったです。
小川氏:最初は余計な手間を取りたくなかったので、できるだけオフィスから近いところで探しました。なかでも洗濯や掃除、食器洗いなどのメイドサービスがついている「サービスアパート」があったので、そこを選びました。身の回りのことをなんでもやってくれて、非常に快適です。
内田氏:私もサービスアパートをインドネシア時代に利用しましたが、確かにおすすめです。特に初めて海外駐在をする人には向いていると思います。家賃は高くなりますが、そのぶん仕事に集中できるのであれば、十分割に合うという感覚です。
――そのほか、赴任当初に苦労されたことはありましたか。
小川氏:手続き上の問題で、現地の銀行口座がなかなか開設できなかったのには苦労しました。時間がかかることは知っていたので、最初の1か月間は数十万円の日本円を持参し、切り崩しながら生活しました。当時は円安が進行していたので、両替するたびに身の縮む思いをしましたね。
現地スタッフに「尊敬される部分」も必要
――初めての海外赴任ということで、業務内容もやはり変化があったのでしょうか。小川氏:180度、まったく違うものになりましたね。日本の本社ではSAPなど他社のシステムを主に扱うエンジニアでしたが、タイでいきなりmcframeなどの自社プロダクトを扱う必要に迫られました。もちろん人手が限られる海外拠点では、エンジニアとしてだけでなく、営業としての動きも求められます。同時に、管理者として採用を含む人事や経理など、バックオフィスも含めた幅広い仕事をしなければなりません。
――海外で、それだけ多様な業務を覚えるのは大変そうですね。受け入れる側の内田さんは、どのようなことを考えたのでしょうか。
内田氏:まず考えたのは、「業務マニュアルを作成したとしても、あまり意味がない」ということでした。タイの拠点は売り上げを拡大していくフェーズですから、日々業務が変わっていくわけです。「やっていくうちに覚える」のが一番良いと判断しました。
そのうえで、私と小川さんの2人体制でいる間に、3か年で徐々に仕事を移譲していく計画を立てました。具体的には、1年目は「修業」として現場で営業やシステム導入支援に当たってもらう。2年目から私の責任下で管理業務にも携わってもらい、3年目で小川さんに管理業務の主導権を握ってもらう——そんな流れです。計画通りに運べば、最後は私が楽をさせてもらえるとひそかに期待しています(笑)。
――小川さんを迎える前に、普段からやっておいて良かったことはありますか。
内田氏:拠点のシステム化を進めたことですね。着任当初に「遅れているな」と感じたので、販売や購買、営業活動を管理するシステムの導入を進めました。仕事の効率化という狙いもありますが、現地スタッフの仕事が可視化できて、管理しやすくなるんです。意図していませんでしたが、それが結果的に仕事を円滑に引き継ぐ下地にもなりました。
――小川さんは、どのような流れで仕事に慣れていきましたか。
内田氏:約45人いる現地スタッフの顔と名前、その担当業務を覚えることが最優先でした。タイには「チューレン」というあだ名の文化があるので、最初の1週間くらいであだ名と顔を必死で覚えました。公的な書類などで使う本名は別にあるのですが、社員同士はあだ名で呼び合います。現地スタッフとの関係を築くことを優先し、余裕ができたら自社プロダクトの仕様も勉強するような感じでした。
――現地スタッフに業務を教わることもあると思います。関係を築くうえで意識していることは何ですか。
小川氏:とにかくコミュニケーションしやすくすることですね。現地のスタッフにとって私は「外から来た人」ですから、前提として、あまり本音をぶつけてもらえない。都合の悪いことがあれば、報告が上がってこない可能性もあります。まずは「どんなに悪い情報も正直に、タイムリーに共有してもらう」ことを目指しています。
もちろん砕けた関係になりすぎるのも考えものですから、そこは私たちに「尊敬される部分」が必要なのだと思います。重要な決断を下すこととか、プロジェクト進捗管理の勘どころを押さえていることとか。うまく本音を引き出しながら信頼関係を構築して、結果的に現地スタッフの成長を後押しできることが理想ですね。
「お客さまのため」は同じ
――「こうすれば良かった」という反省点はありますか。小川氏:赴任前に、日本本社内の関係部署でのあいさつ回りが十分にできなかったことですね。
私の場合、タイで初めて自社プロダクトを扱う立場になり、仕様やサポートに関して日本の本社に問い合わせる機会がたびたびありました。専門用語が違ったり、他社製品とは仕様が大きく違ったり、そうした内容が多くて相手に気を使うんです。せめて出国前に顔合わせだけでもしていたら、もっとスムーズにやりとりできた気がします。
もちろん実際は直前まで私の仕事も立て込んでいて、できる範囲ではやってきました。でも後から「会っておくべきだったな」というキーパーソンが次々出てくる。1か月間兼務するとか、営業に同行させてもらうとか、そうした会社側の配慮があるとより良かったのかもしれません。
――お話を聞いていて、海外で暮らすことに加えて、仕事も覚えなければいけない大変さを感じました。
小川氏:海外駐在では、権限や裁量は格段に大きくなり大変な部分もありますが、バックオフィス業務も含め、日本では関わることのなかった新しい領域に挑戦でき、引き出しが増えている実感があります。プレッシャーもありますが、キャリアにプラスになっているのは間違いないと思います。
一方、「お客さまのためになることをする」「一緒に働く人にも幸せになってもらう」というゴールは日本と変わらないんですよね。仕事を通じて、お客さまと現地スタッフに成長してもらう。物事を判断するときには、その発想からブレないように意識しています。
内田氏:海外生活は大変なことも多いですが、裏を返せば機会がそこら中に転がっているということです。そこをポジティブに楽しめるかどうかが問われると思います。自分が「外国人」として暮らすなかで、現地のコミュニティーに溶け込むだけでなく、時にはタイにいる欧米人とも交流を広げるくらいの積極性が重要なのではないでしょうか。
――海外赴任後、スムーズに仕事をこなすためのコツはありますか。
小川氏:とにかく公的な手続きなどの「日本でやらないといけないこと」「現地でやらないといけないこと」を調べて、早々に片付けておくことが重要です。「あの申請、いつまでだっけ」ということを気にしていると、仕事にも集中できませんから。
心構えの面では「自分の当たり前を、当然だと思わない」ことですね。海外で働くと、自分の常識が覆されることがたびたび起こります。育った環境がまったく違う人と過ごすわけですから、自分の常識を振りかざすマインドでは、物事は運ばなくなってしまいます。
――今後のタイ駐在生活における抱負などはありますか。
内田氏:我々の手掛ける「BtoB業界のIT化」という文脈では、タイは成長の余地が大きい市場です。システムを導入したものの、活用できていない現場も少なくない。伸びしろがあるなかで、1年1年を必死に働いて、事業を大きくしたいと思っています。
あと、私が離任して小川さんの一人体制になったら、全てを破壊してほしいです。前任者の路線を否定して、現地スタッフにも「トップが変わったら組織は変わるんだ」と新鮮に思ってほしい。それって大事なことだと思うんです。潜在能力を引き出すきっかけにもなる。単なる「引き継ぎ」じゃつまらないので、大胆に動かしてほしいですね。
小川氏:「破壊」と言われてしまうとちょっと喋りにくいですが(笑)、内田さんの言いたいことは分かる気がします。B-EN-Gタイは前身から数えると創業20年になり、会社としては成長~成熟期にあります。事業拡大をしつつ、何か変化を起こさないと衰退期に向かってしまうかもしれない。自分が離任する時も「まだ成長途上」という道筋がつけられるように、果敢な挑戦を忘れないようにしたいですね。
(文・共同通信デジタル)
※本記事は2025年2月現在の内容です。