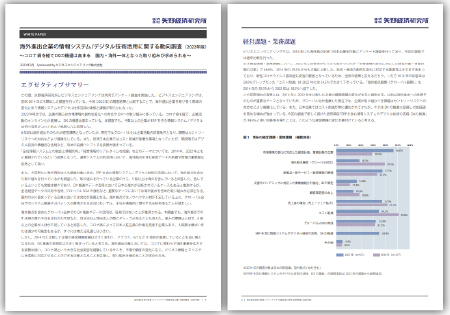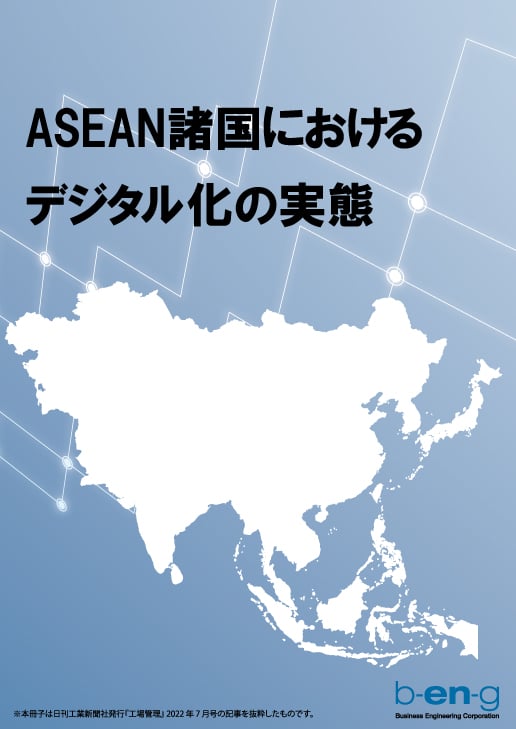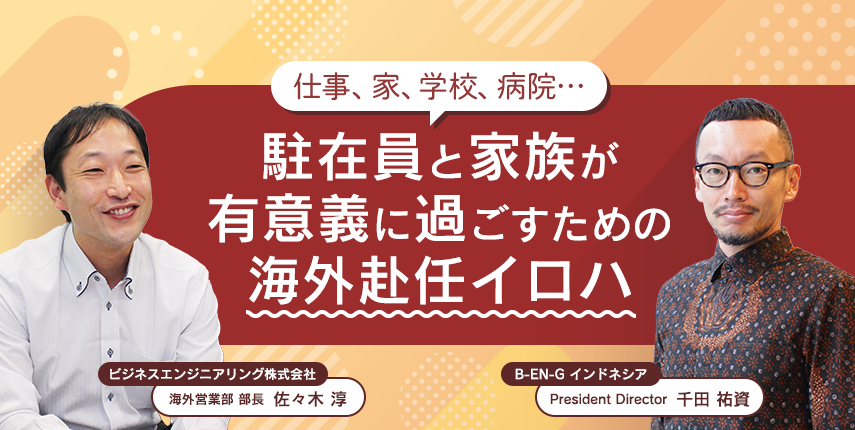あるのは「若い人材」、日本に求めるのは「技術と品質」… 識者に聞くベトナム経済との向き合い方

東南アジアのなかでも経済成長が著しく、注目を集めているのがベトナムです。日系製造業の拠点数では世界5位(2024年2月現在)となっています。デジタル人材の増加も相まって飛躍が期待されているなか、日本企業は今後、ベトナムの企業や人々とどのような関係構築を目指すべきなのでしょうか。日越ビジネスに詳しい2人の専門家に話をうかがいました。
【話者紹介】

カオリ(Nguyen Thi Thanh Huong)
INNOVE PLM Solutions Co., Ltd. 代表取締役社長
ベトナムで製造業向けのIT企業を起業、経営しており、日本企業との取引経験が豊富。広島大学への留学も含め、日本で約3年間過ごしたことがある。ニックネームの「カオリ」は、自身の名前を直訳すると「香り」となることから。

タン(Vo Duc Thang)
VIET JAPAN PARTNER CO., LTD Founder & CEO
大学卒業後、ベトナムに展開していた日本企業のIT子会社に入社、後に日本での勤務も経験した。2018年、ベトナムに帰国し起業。日系企業のベトナム進出と現地展開をサポートしているほか、日本企業とベトナム企業のビジネスマッチングプラットフォーム(登録社数約600社)を運営している。

【モデレーター】渡邉祐一(わたなべ ゆういち)
ビジネスエンジニアリング グローバルビジネス推進本部長
2000年、B-EN-Gに入社。主に製造業向けのERP関連業務に従事。2011年よりタイ拠点に赴任しmcframeビジネスの組織を立ち上げ。プロジェクトマネージャーとしてタイ国内で複数のシステム構築を経験した。その後、タイ現法長としてタイ拠点全体をマネジメント。2023年に日本に帰任しグローバルビジネス推進本部長に就任し、現在に至る。
ベトナム経済、最大の魅力は「若い力」
渡邉:ベトナム経済は高い成長率で世界から注目を集めています。まず、その全体像を俯瞰していただけますか。カオリ:昨年(2024年)のベトナムのGDP成長率は7%を超え、今年に関して言えば、政府はさらに高い8%の目標を掲げました。科学技術のイノベーションや民間経済の発展に力を入れる方針を鮮明化させており、2050年をターゲットに先進国となることを目指しています。

その原動力が「若さ」です。平均年齢31歳のベトナムは、35歳以下の人が6割超を占めます。働き盛りの人材が豊富で、政治体制も比較的安定していることから、海外企業からは投資しやすい環境になっているようです。
タン:人口構成が若いことに加えて、どの世帯も教育熱心です。収入の大部分を子どもの勉強に投資している親が多い印象です。
IT領域においては、各大学に専門の学部が設けられるなど「国策」として注力されてきました。10年以上前はITエンジニアの人手不足が課題でしたが、今日のベトナム国内の労働市場はIT人材であふれています。
渡邉:確かに、ベトナムにオフショア拠点を設ける企業が増えている印象があります。産業構造全体は、どのようになっているのでしょうか。
カオリ:経済全体で見れば、依然として柱になっているのが製造業です。韓国・中国企業がベトナムに多くの生産拠点を進出させており、対米輸出も多くなっています。ただ、IT産業やDXが今後のトレンドになることは間違いないでしょう。ほかにもインフラ整備や不動産開発、そして脱炭素化に関わる産業も脚光を浴びることになりそうです。
経済成長に伴い、富裕層の消費が活況
渡邉:そんななか、日本からの投資や日本企業の進出はどのような状況になっていますか。この状況は、ビジネス文化によるところも大きいと思います。日本企業の視察・訪問は依然として多いのですが、判断までに時間がかかっています。ほかの海外企業は決裁権を持つ人が訪問し、その場でOKが出ていることが多く、そのスピード感の違いで差がついている気がしますね。
渡邉:具体的に、ベトナムに進出している日本企業や業界の目立った動向はありますか。
タン:飲食店やホテルなどのサービス業が進出し始めている印象です。経済成長に伴い、ベトナム国内の富裕層が厚みを増していることが背景にあるでしょう。富裕層は品質のいいモノやサービスを求めていて、メイド・イン・ジャパンへの信頼も根強い。そこに商機を見いだしている会社が進出してきています。

特に、いまの若者を見ていると「美味しいものを食べたい」「いいものを持ちたい」という消費意欲が高いですね。平均年収の伸びを上回るペースで消費が活発になっているように感じています。
渡邉:日本企業の進出に対し、ベトナム側はどのようなことを期待しているのでしょうか。
カオリ:何といっても「技術」です。製造業において海外企業がベトナムに持ってくるのは製造工程だけで、設計や開発機能はなかなか移管してくれません。この構図のままでは、「日系企業の工場で30年働いても、働く人はあまりスキルが身につかない」ということが生じてしまいます。
ただ、直近では半導体設計の開発機関に1,000人超のベトナム人エンジニアが採用されたケースもありました。政府側もいろいろな優遇制度を整えていますし、今後そうした先端産業にもどんどん進出してもらえることを期待しています。
タン:ベトナムは働き手が若いので、全般的に経験不足です。プロセスの管理など、先のことを考えて動くことが苦手なので、その点で日本企業から教わることは多いと思います。日本はビジネスの完成形を知っているので、ベトナムの現状を見て、何が足りないのか分かるでしょう。それが現地にとっては貴重な参考情報になると思っています。
能力に応じた給料を払わないと、引き抜かれてしまう
渡邉:実際に、日本企業がベトナムに進出するにあたって、どんなことに気を付けるべきでしょうか。タン:「日本で成功したから、同じようにやってくれ」というのはダメですね。それで失敗し、撤退した会社が多いです。ベトナムは「親日国」と言われていますが、やはり文化の違いはあるわけなので、意識する必要があります。
渡邉:日本人や日本の組織は保守的で、決断に時間をかけることが多いですからね。
タン:人材確保の面でも、このスピード感の違いは大きな影響を与えます。私も日本で勤務した経験がありますが、日本企業の昇給は年間で数千円とか、多くても3万円くらいでしょう。スキルアップをしても、給与は2倍、3倍にならない。しかしベトナムでは能力に応じた給料を払わないと、良い人材はすぐに引き抜かれてしまいます。
これは待遇の話に限りません。「長く働いてもらおう」と思って長期間の研修をすると、「仕事を任せてもらえない」と感じたスタッフは退職してしまいます。ここの感覚が分からないと、日本人は戸惑ってしまうかもしれません。
ある日系企業では社内の公用語を英語にしていて、そうした環境整備の結果として採用も比較的好調だと聞いています。
「何を期待しているのか」をきちんと伝えること
渡邉:スピード感の違いに関する話は印象的でした。仕事への考え方や、働き方に関する文化のギャップもあるのでしょうか。カオリ:一般的に、ベトナムの会社は日本企業よりもフラットな雰囲気だと思います。厳しい上下関係はなく、社内で声をかける時も日本の「〇〇部長」のように役職では呼ばない。職場でも家族同士のような、アットホームな人間関係を形成していることが多いです。
半面、ベトナム人は家族よりも仕事を優先することは少ないですね。単身赴任が命じられても、辞退することもあると思います。子どもの誕生日には残業を断ることもあるでしょう。大事なのは、これは本人が「怠け者」だということを意味しないことです。家族を大事にする文化なのだと理解してほしいと思っています。
タン:仕事への考え方では、任された仕事の「どこまで責任感を持つか」という点で、日本とベトナムでは違いがあると思います。ベトナムでは「指示されたことを終わらせればOK」が基本ですが、日本では関係者のことまで気を遣い、組織やプロジェクト全体の結果にコミットするところまで追求することが多いですよね。その認識が合わないと、後からトラブルになりかねません。
ベトナム人に仕事を任せる時は、仕事の内容を明確に定義することが大切です。「何を期待しているのか」「どこまでやってほしいのか」をきちんと伝え、達成したらちゃんと感謝し褒めることで、業務が円滑に進むと思います。
カオリ:あとは歴史的経緯による国民性や文化にも特徴があります。ベトナムは厳しい戦争を幾度も乗り越えてきた歴史があり、プライドが高い人も多いです。厳しく叱責すると反感を買ってしまうことがあるので、気を付けてほしいと思います。
また、同じ経緯からベトナムは女性の社会進出が進んでいるという特徴もあります。男性が戦地に赴くことが多く、女性が家事も仕事もする時代が長かったことも影響しているのでしょう。専業主婦世帯が少ないということも、背景知識として持っておくと良いのではないでしょうか。

渡邉:参考になるお話ばかりでした。改めて、日本の読者に伝えたいことはありますか。
カオリ:繰り返しになりますが、日本には先端技術に関わる投資を期待しています。仮に好待遇でも、古いビジネスばかりをやっていては面白くないし、スキルも身に付かない。まして技術が伝承される前に、AIによって自動化されてしまうようでは意味がないです。ベトナムの人材にもできることはたくさんあるので、成長につながる機会をぜひ提供してほしいと思っています。
タン:技術レベルは日本に及びませんが、ベトナムの若者もみんな頑張っています。若者特有の柔軟さや創造性もあります。ベトナムにあるのは「人材」で、日本をはじめ外国に求めるものは「技術」と「品質」です。一緒に発展して新しい価値を作るための、win-winの関係が築けることを希望しています。
渡邉:お二人が仰る通りだと思います。一緒に発展できるような関係が築けるよう、私も頑張ります。
タン:一緒にやりましょう。

(文・共同通信デジタル)
※本記事は2025年7月現在の内容です。